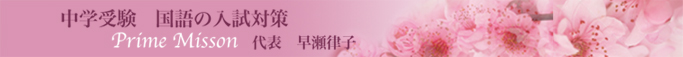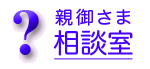<二学期から入試本番までの(四教科の)学習について>
〜教科別 6年生の学習スケジュールのサンプル〜
学習方法について模索されている親御さまのお問い合わせの中には、国語に限らず他教科についてのご質問も多く、そのご要望にお応えするために全教科の学習方法に触れることに致します。
二学期が始まると塾の模擬試験がどんどんと増えていきます。塾の方でも、志望校別に新しいカリキュラムの授業が増えていき、土曜日、日曜日でさえも家庭学習の時間が思うように取れなくなってくるというのが実情です。
しかし、この時期からは、本格的に志望校を決定し、その志望校の過去問の演習を徹底的に行わなければなりません。
なんといっても入試本番まであと少しです。
学習を停滞させることなく、大きな目標を掲げ、毎日必ず前進していくことが肝要です。
全教科に共通してこの時期に重要なことは、次の4つです。
*自分の弱点を完全に克服する!
*今まで学習してきた知識を繰り返し確認することで記憶に保持する!
*応用力に磨きをかける!
*志望校の傾向をよく分析し対策を万全にする!
まずは、教科ごとに今までに学習してきた知識が確実に身についているのかどうかを確認して下さい。塾で行った模試の結果を見直して、その都度丁寧にお子さまがミスをした箇所の分析を行い、できなかった項目をしっかりと学習することをお勧めします。
そして、「理解が足りなかった部分はないか」、「抜け落ちている知識はなかったか」を再確認した上で、その項目の知識を確実に定着するための学習をして下さい。
コツは、第一に、確認したその日のうちにその部分を学習してしまうことです。
そうです、補習するべきことが明確になった時点ですぐに取りかかることが大切なのです。
今日やるべきことを延ばし延ばしにすると、時間の経過と共に、明確であった「理解の不足部分」「知識の抜け落ちの部分」が曖昧になります。
そして、もともとその部分の内容はお子さまの苦手な項目であることが多いので、時間が経てば経つほど学習するのが苦痛になる可能性があります。
大人でさえも、やはり苦手とすることは先延ばしにしたいという気持ちが働きます。
しかしそうやってズルズルと先延ばしにしてしまったことで、後悔したことは誰にでも経験があるのではないでしょうか。
たとえ億劫に感じても、その時点に頑張ってその苦手とすることをクリアーにしてしまった方が結局は効率がいいのです。
ですから、定着していなかった部分を発見したらできるだけ早いうちに復習しておくようにして下さい。
第二に、疑問点をそのまま放置しないことです。
この学期は塾で多くの演習問題を解かなければなりません。
その時に「わからないことをわからないままにしておく」ことで、その次のステップへ進む際にますますわからなくなってしまいます。
つまり理解の不足が時間の経過と共に助長されてしまうわけです。
ですから、授業中に理解できなかった問題をそのままにせず、家庭学習ですぐにその部分の学習をやり直します。家庭学習の際に解けなかった場合は、すぐに学習指導をして頂いている先生に質問して完全に理解しておくことです。
弱点補習は、できれば夏休み中に完了しておくことが理想的ですが、もし、弱点補習がまだの場合は、この時期が最後のチャンスだと思い、諦めずに必ず克服して下さい。
今回は、たくさんの親御さまのお問い合わせにお応えするために、二学期から入試直前まで我が子が中学受験に向けて実行した全教科の学習スケジュールを教科別に掲載致しました。
もし、有効だと思われる内容がございましたら参考にして頂ければと思います。
<国語>
国語の入試直前までの学習は、『親御さま相談室』の「6年生 秋からの国語の学習方法のサンプル」の中でも触れておりますが、一番大切なことは、「その都度理解しておく」ということです。(その点は全教科共通です)
特に国語の読解問題は、塾のテキストの問題を解いた際に、「どうしてこの設問の正解がこうなのか」ということが理解できないままに学習していても読解の実力をつけることができません。
ですから、本格的に志望校の過去問の学習に入る前に、絶対に妥協せずに行って欲しいことは、
第一に問題文の大意(要点)を正しく捉えることです。
国語の読解でもっとも大切なことは「正確な読み」です。これなくして設問に対応できるわけがありません。『答え探しの技で勝つ!』の中でも述べておりますが、まず本文の内容(どこにどんなことが書かれていたのか)を理解し記憶させる訓練が必要になります。
第二に設問の正しい読みです。
設問文はたった数行の文章ですが、実はこの設問を正しく読むのは小学生にとって非常に難しいことなのです。数行であるが故にお子さまは油断して読み間違えてしまうのです。
親御さまは、必ずお子さまが誤答をしてしまった際に「設問を正しく読んでいたかどうか」をチェックするようにして下さい。
第三に、設問に対応するための情報を問題文の中から検索できているかどうかです。
国語が苦手なお子さまや国語の成績に波があるお子さまは、実はこの検索するテクニックがまだ身についていないケースが多いのです。
ですから、親御さまは、お子さまが誤答してしまった際に、「きちんと問題文の中から設問の答えの情報をキャッチできたかどうか」を必ずチェックするようにして下さい。この「第一から第三まで」をきちんとクリアーできるようになっていれば、第一志望の過去問やその傾向に即した読解問題を解く際にかなりスムーズに学習が進むはずです。
毎日の学習スケジュールとしては、まず、毎朝学校に行く前に今まで覚えた漢字と知識問題の確認をしました。
そして、夕方から夜にかけては「毎日国語の読解問題に取り組む」ということを前提に学習計画を立てました。
塾で国語の授業がある時には、授業中に集中してしっかり学習し、疑問点もその場で質問をし、きちんとクリアーにしておきます。
そして、その日の家庭学習としては、授業中に学習したことを本当に理解しているかどうか、簡単な口頭試問を行いました。
これは、わずか15分くらいしかかかりませんので是非やってみて下さい。
このほんの少しの復習が理解を深めます。
一方、塾で国語の授業がない日には、家で必ず時間を計って読解問題に取り組み、答え合わせや誤答してしまった部分の見直しをしました。
主に使用した教材は、塾で頂いた『中学入試過去問題集』です。まずは、いろいろな特徴の文章や設問に慣れるために志望校にこだわらずどんどん解くようにし、その段階を経てから本格的に志望校対策の学習をしました。
だいたい11月までにさまざまな学校の入試問題に触れて柔軟性を養い、
12月からは自分の志望校の過去問を徹底的に解きました。
そして翌年1月は今までの(志望校の過去問中心)総復習をし、入試本番に備えました。
(11月のある一週間の学習スケジュールの例)
○日(日)・・・(塾の国語の授業があるので)塾の授業中に学習
○日(月)・・・「説明文の読解問題」 ○○校 平成○年度の問題を学習
○日(火)・・・塾の国語の授業中に学習
○日(水)・・・「物語文の読解問題」 ○○校 平成○年度の問題を学習
○日(木)・・・「論説文の読解問題」 ○○校 平成○年度の問題を学習
○日(金)・・・「随筆文の読解問題」 ○○校 平成○年度の問題を学習
○日(土)・・・塾の国語の授業中に学習
*漢字の学習、知識(ことわざ、慣用句、四字熟語、文法など)の確認は、必ず毎朝学校に行く前に行う。
以上のようにリズムを作って学習に取り組みました。この時期にさまざまな文章に触れ、またいろいろな切り込み方の設問に対応する柔軟性を身につけておくと、志望校の過去問を解く際にも非常に役に立つと思います。
<社会>
二学期が始まってから11月下旬までの社会の学習は、「夏までに記憶させた知識がどの程度身についているか」を確認することに終始しました。
まず、歴史については、時代ごとに毎日問題を解くことで記憶の定着が確実になされているかどうかをチェックしました。
この時期は、塾から頂いた『中学入試過去問題集』をよく利用しました。
学習方法としましては、一週間ごとに日曜日から土曜日までに学習する時代を決めてスケジュール表に書き込みます。
そして、徹底的にこの『中学入試過去問題集』を使用し、学校にこだわらず全部解いていくのです。
その日に学習する内容が「江戸時代」だった場合、『中学入試過去問題集』に掲載されている「江戸時代」の問題をすべてコピーして解いていきます。
例えば、開成、慶応中等部、学習院、女子学院、麻布、早稲田実業で「江戸時代」の問題が掲載されていれば、その部分の問題だけをコピーして全部解いていきます。
(11月のある一週間の学習スケジュールの例)
○日(日)・・・縄文〜奈良時代に関する問題を問題集からピック・アップして解いていく
○日(月)・・・平安時代の問題を解く
○日(火)・・・室町時代の問題を解く
○日(水)・・・安土桃山時代の問題を解く
○日(木)・・・江戸時代の問題を解く
○日(金)・・・明治時代の問題を解く
○日(土)・・・大正時代の問題を解く
○日(日)・・・昭和〜平成時代の問題を解く
そして、再びその次の週の月曜日からは、「縄文〜奈良時代」に関する問題を解いていきます。火曜日は、室町時代、水曜日は安土桃山時代・・・・というように毎週繰り返して全時代の学習を行います。
すると、どの時代のどんな事がらが、記憶から抜け落ちてしまっているのかがはっきりとしてきます。また、その事がらは暗記できていても、問題の切り込み方によっては、答えられない部分を発見できます。
問題に躓くということは、暗記していても本物の知識として身についていないということに他なりませんので、その時代の「事件」「リーダー」「政治」「経済」「文化」「時代背景」を塾のテキストでもう一度確認しました。
地理の学習は地方ごとにスケジュールを立てました。例えば、毎日、以下のスケジュールのように学習を行っていました。
(ある11月の一週間の学習スケジュールの例)
○日(日)・・・北海道地方
○日(月)・・・東北地方
○日(火)・・・中部地方
○日(水)・・・関東地方
○日(木)・・・近畿地方
○日(金)・・・中国・四国地方
○日(土)・・・九州地方
翌週も日曜日から、再び北海道地方の学習を始め、東北地方、中部地方、関東地方・・・と繰り返し学習し、記憶の定着を図りました。
このように、その日に学習すると決めた地方については、まず市販の『白地図ノート』をコピーし、それをテストとして使用し、すべてきちんと覚えているかどうかを確認しました。
そして、その『白地図ノート』が全部クリアーできたことを確認した後で、『中学入試過去問題集』を使用し、その日学習すると決めた地方についての問題を学校にこだわらず、すべてピックアップしてどんどんと解いていきました。
さらに、12月に入ってからは志望校の過去問を徹底的に解きました。
もし問題が解けなかった場合は、そこの部分を、塾のテキストで時間をかけて復習し理解と記憶の定着に努めました。
公民については、11月までは基本的な事項を大まかに分類し、その内容を計画的に毎日一つずつ確認していきました。
確認のために使用していたのは塾のテキストでした。知識の確認ですから、時間をかけず短時間でリズムをつけて解答するようにしました。
(11月のある一週間の学習スケジュールの例)
○日(日)・・・「日本国憲法」
○日(月)・・・「日本国憲法」
(憲法は知識として取り入れたいことが多いので学習に2日間を費やしました)
○日(火)・・・「三権分立」「国会」
○日(水)・・・「内閣」「裁判所」
○日(木)・・・「地方自治」
○日(金)・・・「財政」「社会保障」
○日(土)・・・「選挙と政党」
○日(日)・・・「国際連合」
○日(月)・・・「環境問題」
11月まではこのように学習スケジュールを立て、基本的な内容を確認し、その後は一日一校のペースで『中学入試過去問題集』を使用して問題を解いていきました。
公民の場合は、項目別に分けて問題を解くというよりも、覚えるべきことを覚えてしまったら、どんな方向から質問されても答えられる柔軟さを重視した学習をどんどんと進めた方がよいと思います。
その他、政治や経済に関するニュースを頻繁にテレビで見るようにしていました。
この時期は、塾に通う日数も増え、なかなかタイムリーにテレビを見ることが難しくなりますので、必要だな、と感じたニュースはビデオに撮り、勉強の合間の休憩時間に見るようにしていました。
やはり、映像を通して視角が刺激されると、インパクトが強く、その内容が自然と頭に入っていくようでした。
気分転換にもなりますので一石二鳥だったと思います。
そして、12月に入ってからは、本格的に第一志望校から第三志望校の過去問を繰り返し解き対策を万全にしていきました。
<理科>
理科の学習につきましては、すべてを項目別に分けて下記のようにスケジュールを立て、『中学入試過去問題集』を使用して様々な問題を解くようにしました。
まず11月までは学校にこだわらず、その項目についての問題が掲載されているものをすべて解くようにしました。
同じ項目についての問題でも、理科の場合は、その学校によって質問形式が異なり、その設問に対応する力を徹底的につける必要を感じましたので、学校別にそれぞれの問題を細かく分類して学習スケジュールを作成しました。
↓
「物理編」「地学編」「植物編」「動物編」「化学編」に分けて、1週間ごとにその分野を徹底的に学習することにしました。
主に『中学入試過去問題集』を使用し、その分野を出題している学校の問題を手当たりしだいに拾い出してコピーを取り解いていきました。
例えば、ある一週間を「物理編」と「地学編」の学習を行うことに決め、次のようにスケジュールを立てて学習します。
(11月第一週目のスケジュールの例)
「物理編」
○日(日)・・・「物体の運動」ラサール、「力学」芝中、「光」麻布
○日(月)・・・「バネ」城北1次、「てこ」城北2次、「音」聖光
○日(火)・・・「てこ」桐蔭、「物体の運動」東邦大東邦、「音」灘
○日(水)・・・「とつレンズ」海城、「バネ」市川、「物体の運動」慶応普通部
「地学編」
○日(木)・・・「月」浅野、「惑星」鴎友、「鍾乳石」渋谷
○日(金)・・・「太陽」早稲田、「天体」慶応中等部、「水の循環」双葉
○日(土)・・・「台風」桐朋、「地層」市川、「岩石」巣鴨
このように1週間のスケジュールを立てておくと多種多様な質問形式の問題に取り組めます。
これと同様に第2週は、「植物編」と「動物編」、第3週目は、「化学編」と「物理編」・・・・・というように繰り返していきます。
つまり、「地学編」→「植物編」→「動物編」→「化学編」という流れを繰り返していくのです。
すると、驚くほど、どの項目が苦手なのかがはっきりしてきます。
特に理科の場合は、様々な学校の問題に取り組むことによって、自分としては、得意だと思い込んでいた項目でも、質問の切り込み方が違うと答えられないものがはっきりとあぶり出されますので、この学習方法はお勧めです。
理科につきましても、11月までは、「何ができて何ができないか」、つまり、「どんな知識が定着していなかったのか」「何をきちんと理解していなかったのか」ということを発見する最後の時期です。
入試直前に慌てないようにここでしっかりと自分の弱点を知っておくこと、そして、その弱点を克服すべく学習をし、揺るぎない自信で入試を迎えることが大切です。
また、基礎的な学習を踏まえて応用力に磨きをかけられるのもこの時期です。さらに、12月に入ったら第一志望校から第三志望校までの過去問をどんどんと解いていき、翌年1月には12月に解いたものを繰り返し何回も見直すというように、総復習をして対策を万全にしました。
さまざまな質問形式の問題を項目別にチャレンジすることで大きな力を培い、「よし、どこからでもかかってこい!」という意気込みで入試本番に臨んで頂きたいと思います。
<算数>
算数の学習計画はあくまで塾のスケジュールのリズムに合わせて立てるようにしました。
朝は、毎日学校へ行く前に塾から頂いた問題集(計算問題を含めた算数の基礎となるトレーニング「基礎トレ」)を欠かさずStop Watchで時間を計って行い、答え合わせをして間違えたものはすぐに解き直しをしました。
学校から帰宅してからの学習は、次のようにスケジュールを立てました。
まず、塾で算数の授業がある日は、塾から帰宅してすぐに、塾の授業で行った問題を含めて、その日頂いてきたテキストを最初から最後まで一冊すべて解くようにしました。(Sapixでは、授業で毎回一冊のテキストが配られますのでそれを使用しています。塾の先生が、解く必要のない問題だと判断した問題は除外しています)
一方、塾のない日は、『中学入試過去問題集』(あらゆる中学校の過去問が編集してある、電話帳とよばれるもの)を使用し、志望校にこだわらず、さまざまな学校の問題に取り組みました。どの項目のどんな問題でも対応できる力を養うこと、そしてケアレス・ミスをしないことを目標にしました。
(11月のある一週間のスケジュールの例)
○日(日)・・・(塾で算数の授業があるので)塾で集中して学習
帰宅後は塾で頂いたテキストをすべて解く
○日(月)・・・○○校 平成○○年度 入試問題
(四則計算、速さと比、旅人算、つるかめ算、周期算)
○日(火)・・・○○校 平成○○年度 入試問題
(時計算、平面図形、規則性、場合の数、割合と比)
○日(水)・・・○○校 平成○○年度 入試問題
(四則計算、過不足算、立体図形、表の読み取り)
○日(木)・・・(塾で算数の授業があるので)塾で集中して学習
帰宅後は塾で頂いたテキストをすべて解く
○日(金)・・・○○校 平成○○年度 入試問題
(約数・倍数・素数、食塩水の濃度、推理算、平均算)
○日(土)・・・(塾で算数の授業があるので)塾で集中して学習
帰宅後は塾で頂きたテキストをすべて解く
二学期がスタートした頃は、このように、できるだけ多くの項目をまんべんなく学習し、偏らないようにしました。そして、11月半ば頃からは第一志望校の傾向を加味しながら取り組む問題を選択するようにしていました。そして、入試対策のために自分の第一志望校から第三志望校までの過去問を12月中旬までに解き、翌年1月に入ってからは、それを繰り返し復習して入試本番に備えました。