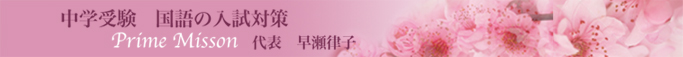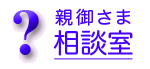<お子さまを叱る時には>
「できれば叱りたくなんかない」というのが大方の親御さまの気持ちではないでしょうか。
子どもを叱るのは本当にエネルギーが必要ですし、叱った後の後味の悪さはたまりません。
子どもを叱る場面というのは、日常生活の中で挨拶の仕方や食事のマナーなど、子育てをしていればそれこそたくさんあると思いますが、今回は「受験を控えたお子さまを叱る時」に焦点を絞り、いくつかの場面を想定してアドバイスを述べさせて頂きたいと思います。
特に受験を直前に控えたデリケートな時期は、親御さま(特にお母さま)にも心身への負荷がかかりたいへん疲れておりますし、お子さまも「学校生活」と「塾の学習」の両立で忙しさがどんどんと増してきます。
つまり、親子で余裕のない状態が長く続くことになります。
理想を言えば、勉強のことについてお子さまを叱らないで欲しいのですが、受験生の場合はそうもいかない現実があります。
しかし、ここで親としての冷静さを保ち、「本当に叱るべき場面かどうか」ということを見極めることが大切だと思うのです。
例えば、テストの結果の悪さや塾の学習の不出来だった点を責めるために叱って欲しくはありません。
できるだけ、その時はこらえて叱らないであげて欲しいのです。
お母さまが叱りたい気持ちはわかります。
何か一言、言いたい気持ちも痛いほどよくわかります。
でも、こういう時に叱りつけてもいいことは何にもありません。
それから、お母さまがお子さまの学習をみている時にお子さまがその問題を解けなかったからといって叱らないで欲しいのです。
ましてや解けなかった時に「この問題このまえやったばかりじゃないの、何度教えたらわかるのよ!」などと叱りつけるとかえって事態を悪い方に向けてしまいます。
そのような叱り方はお子さまの学習意欲を減退させてしまいますし、お母さまの長い小言はお子さまの心を疲弊させます。
そして何よりもお母さま自身が怒りをお子さまにぶつけてしまった結果すっきりするどころかさらに心身ともに疲れてしまうことになります。
それは当然、時間の無駄にしかならないのです。
小言を言っているその時間を学習時間に当てた方がよっぽどいいに決まっています。
ですから、こういう時はゆっくりと5回以上の深呼吸をして、ご自分の日記なりメモ帳なりにお子さまのいいところを何か見つけて最低でも5つ書くようにして下さい。
例えば
・今日学校へ行く時に「いってきまーす!」と元気に挨拶ができた。
・近所の人にも上手に挨拶をしていた。
・お友達にやさしい。
・・・・などなど。
いいところが見つからない、なんてことは絶対にありません。
例えば、「今日も元気に学校に行った」ということだって立派なことであり、褒めるべきいいことだと思います。
学校生活においてもお子さまは集団の中で毎日様々な経験をしているのです。それをしっかり終えて帰ってきたということは大いに立派なことだと思います。そういうお子さまのいいところ、立派なところをご自分の手で書くことによって必ず冷静さが取り戻されていきます。
そして、ご自分のお子さまを認めることによって、「1回や2回のつまずきなんてまた頑張ればいいのだし、どうということはない!」「こんなにいい子なんだものテストの結果が悪かったことなんてたいした問題ではない」と思えてきます。
しかし、受験生である以上、当然学習は日々きちんと行わなければなりません。もし、親子できちんと話し合った結果、お子さまの希望で中学受験をすることに決めた場合のみ、学習をさぼったら叱っていいと私は思います。
何日も学習しなければ当然士気が下がりますし、受験生としての生活リズムが狂ってきます。するとそれはどんどんと悪循環していってよけいに学習をすることが苦痛になってしまいます。
その時は、まず、もう一度、お子さまに
「本当に心から中学受験に臨みたいのか」
↓
「自分の第一志望校を目指して学習することが約束できるか」
↓
「親子で作成した学習スケジュール(そのお子さまに合わせて無理のない有益な計画を立てて下さい)を毎日実行していくことを約束できるか」ということを十分に話し合って下さい。
そしてその上で、学習をサボった場合はやはり親として「自分の決めたこと、約束したことは守りなさい!」と叱るべきだと思います。
しかし、その時も、感情に流されることなく、「これだけは伝えたい」という思いを真剣に言葉にしながら叱って欲しいと思います。
子どもを叱るのは本当に難しいことです。
個人的にお子さまの学習指導に携わらせて頂いている関係で私はよくお母さま方から「この頃よく子どもを叱ってしまうんです・・・」というご相談を受けます。
その際には、「とにかくお子さまを叱る場合は、短く一喝で叱って下さい」と申し上げています。
これは、私が『プレジデント Family』2008年10月号の「毎日三回、短く一喝が子どもの力を伸ばす―母の叱り方・父の叱り方」を参考にさせて頂いた提言です。
この記事の内容は私自身、母親として子どもを叱る際のわが身を振り返って考えるいいきっかけになりました。自分では無意識のうちに子どもを叱る時、つい長いお説教をしていたことに改めて気付かされたのです。
得てして女性というものは、感情が高ぶると論理的な思考が衰えてしまいメリハリなく長々と叱ってしまいがちです。時と場合によっては、1つの事柄からどんどんと話の矛先が違う事柄にまで及んで叱っている内容の軸足が動いてしまうことさえあります。
また、くどくどと同じことを繰り返し言うという行為は、(叱っている方は子どもに間違っていたことを納得させようというつもりなのでしょうが)大抵の場合は、自分が悪いことをお子さま自身が一番よくわかっているのですから、じりじりと詰めよって徹底的に追い詰めるだけなのではないでしょうか。
親としての感情が先走れば、教育的な言葉から段々と単なる小言になってしまう危険さえあります。そうなるとほとんどお子さまにとって益のない叱り方になってしまいます。
そのような事態を避けるためにも、私はご相談を承った時には先に紹介させて頂いた記事を参考にと親御さまに勧めております。日常生活におきましても、私自身が「短く一喝の叱り方」を実行致しましたところ、効果は覿面でした。
「一喝」に自分の伝えたい思いを込めて伝え、あとはこちらがサッと気持を切り替えてしまうのです。「一喝」を有効にするためには、発信するその言葉の中に簡潔に、伝えるべき重要なキーワードだけを盛り込み、長々とした話を持ち込まないことだと思います。
言うべきことはきちんと言い、そしてすぐに気持ちを切り替えるという姿勢をこちらが持っていると、不思議なくらい子どもの方が素直に向き合ってくれます。
「短く一喝」の叱り方は、お子さまの気持ちを追い詰めることを回避できますし、逆に心の中にきちんと響きます。
子どもの人生に責任をもち、真剣に叱ることができるのは、結局は親だけなのだと思います。できれば叱りたくないというのが本音でしょうが、本当に必要な状況だと判断した時であれば、我が子のためと思い愛情を込めて叱るという行為は大切であると思います。
「短く一喝」の中に親御さまの愛情の言葉を込めて伝えればお子さまの心の奥深くまできっとその愛は届くと思います。
*このインフォメーションにおきまして「雑誌名」・「記事のタイトル」の掲載許可をくださいました
『プレジデント Family』の鈴木勝彦編集長に心よりお礼申し上げます。