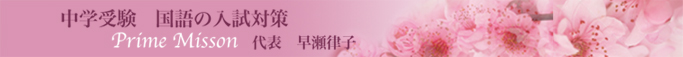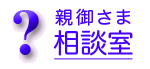<設問文を先に読んだ方がいいのか?>
実は、国語の読解問題の解法は、塾の講師や家庭教師により教え方が違います。よく親御さまから「読解問題に取り組む際には設問を読んでから本文を読んで解いていった方がいいのでしょうか?」というご質問を承ります。
私もかつて我が子が中学受験で塾に通っていた時にしばしば塾の「説明会」や「保護者会」に出席させて頂きましたが、「設問を先に読む」ことを指導する講師の方もいらっしゃれば、「必ず本文を先に読む」と主張する講師の方もいらっしゃいました。
私自身はどうかと申しますと、お子さまの学習指導に携わる際にはずっと、桜蔭中学校の「物語文」の読解問題以外は「まずは本文をしっかり読み、内容を正確に読み取ってから設問文を読む」ことを指導方針とし、それをずっと一貫して通して参りました。
それでは、まず、なぜ桜蔭中学校の「物語文」の読解は設問から先に読むという学習指導方法をとっているのかということをご説明致します。
桜蔭中学校の「物語文」の読解問題は、ここ最近の傾向を見ますと、設問がたったの二問しか出ていないのです。しかも、その二問は非常に難しい記述問題になっております。
では、何故その場合は、先に読んだ方が解きやすいかと申しますと
第一に、設問が二問しかないので、その設問の内容を記憶にとどめておくことが絶対に可能だということです。
たった二問ならば「何を答えるべきなのか」ということを頭の中にしっかりと入れることができます。
第二に、「何を答えるべきなのか」を把握してから本文を読んでいけば「設問の答えの手がかり」をキャッチしやすくなるという利点があります。
『答え探しの技で勝つ!』の著書の中でも主張しておりますが、国語の読解問題は、本文中に絶対設問の答えや答えのヒントが載っています。ですから、その設問の答えの手がかりをしっかり情報検索しながら読み進め、その時に印をつけていき、その手がかりをもとにして記述をしていけば効率的に正解を得ることができるのです。
第三に、桜蔭中学校の入試問題の「物語文」は非常に長い文章になっております。もちろん、「物語文」の大意(要点)をしっかり捉えることさえできれば、本文を読んでから設問文を読んで解いても必ず解けます。
しかし、設問で「何を答えるべきなのか」を頭の中に入れておいてから本文を読み、「答えの手がかり」にアーチの印をつけていけば、(アーチ印の付け方につきましては『答え探しの技で勝つ!』の「記述式問題の解き方テクニック」を参照して下さい)時間の短縮になりますし、「答えの手がかり」を捉えやすくなります。
それでは、何故私が他の中学校の入試における国語の読解問題は先に設問を読むことを学習指導方針としていないのかをご説明致します。
まずは、設問の内容、つまり、「何を答えるべきなのか」ということを把握し、記憶に残しておくのは、せいぜい二問が限界だからです。
他の中学校の国語の入試問題をご覧下さい。
設問の種類は、選択式、抜き出し式、記述式と多岐に渡っており、しかも説問題数が非常に多いと思います。
これらの設問文をすべて読んで果たしてお子さまは「何を答えるべきなのか」ということをすべて把握し、そしてそれを全部記憶にとどめながら本文を読むことができるでしょうか???
そもそも「設問を先に読む」ことの効用というのは、何を答えるべきかという内容を検索しながら本文を読めるということに尽きると思うのですが、設問数が多くてその内容を記憶に留められないならば、何の意味もありません。
しかも、設問文の内容が難しかった場合、設問を読んだ時点で動揺し、本文を読み進める時に注意力が散漫になります。そうなると、正確に本文の要点さえつかみ取れなくなり、できるものもできなくなってしまう恐れさえあります。
ですから、設問文を先に読んでいいケースは設問数が二問以内の時のみという学習指導方法を私はずっと通しております。
桜蔭中学校の入試における国語の読解問題においても、私は「設問数が三問以上の場合は本文から読むように」とお子さまに言い含めて指導をさせて頂いております。
三問になれば「何を答えるべきなのか」を同時に情報検索するのは難しくなります。その正確さが怪しくなるのです。
設問数が少ないということは、一問、一問の配点が非常に高いということです。ここで「答えの手がかり」を大きく外すことは許されません。
ですから、桜蔭中学校を第一志望校にしているお子さまには、念のため「本文を読む→設問を読んで解く」という方法と「設問を読む→本文を読んで解く」(あくまで設問数が二問以下の読解問題のみ)という両方、すなわち二種類の解法を授業で練習して頂いております。
もし、「設問を先に読んで本文を読んだ方が効率よく、しかも正しく解けるのではないか?」とお思いの親御さまは、一度、両方の方法を使ってご自分で実際に解いてみることをお勧めします。
ご自分のお子さまの第一志望校の国語の読解問題(過去問)を使用して、「設問文→本文」の順番で読んで解く方法と「本文→設問文」の順番で読んで解く方法の両方で問題にトライしてみて下さい。
まず、最初に2年前の過去問を使用し「設問を読む→本文を読んで解く」という順番で解き、どのくらい正解が得られるかを確認してください。
次に、1年前の過去問を使用し「本文を読む→設問を読んで解く」という順番で解き、答え合わせをしてみて下さい。
どちらがより解きやすいのか、そしてどちらの方法が正解率が上がるのか、そのことを体感して頂ければご納得頂けると思います。