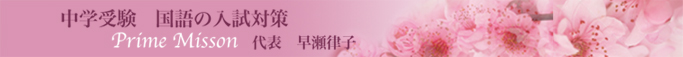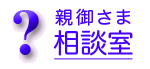<大手進学塾の模試の活用の仕方>
受験というのは、長丁場です。そして、その日学習した成果というのはすぐにテストの結果として現れることは少なく、長い、長い時間がかかります。
今頑張って学習したものは、3か月後、半年後にその成果が反映されることの方が実は多いのです。
ですから、その間に仮に思わしくないテスト結果が出てしまっても、それをいちいち気にせず、そしてリズムを崩すことなく学習を習慣化させ、「途中でくじけない」ことが大切です。くじけないとは、「心をくじけさせない」ということです。
まずは、テストの結果に一喜一憂しないで下さい。
経験則から申し上げても、例えば、「志望校別テスト」などで、合格の可能性が80%と出たから必ず合格、20%と出たから可能性がないということはありません。ましてや、その結果をすべてだと思い込み、落ち込む必要などありません。
したがって、テストの点数にこだわるのではなく、むしろ、そのテストの結果を踏まえて弱点を丁寧に分析し、その部分を徹底的に補習して次のテストに備えるというリズムを作っていくことが肝要です。
むしろ、結果が良くなかった時ほどチャンスです。
何故なら、受験本番を迎える前に自分の弱点が浮き彫りになったからです。
まずはどのような問題を間違えたのかをチェックして下さい。
↓
- 漢字や熟語などの語彙、ことわざ、慣用句、文学史、文法などの知識問題で落としている場合は、その部分を徹底的に復習します。
- 読解問題の場合は、「説明文」「論説文」「物語文」「随筆文」の中のどのジャンルの文章が苦手であるかを確認します。そして、確認できたらなるべくその苦手な文章に慣れるよう、そのジャンルの文章をたくさん読むようにします。
例えば、「論説文」の問題で点数が取れなかった場合は、重点的に「論説文」を読むようにして下さい。
理想的なのは、「論説文」の読解問題を実際に解くことですが、塾の授業や宿題に追われて時間的な余裕がないお子さまも多いと思います。
そういう場合は、「論説文」を読むということだけでも効果はあります。
ただ読むのではなく、読みながらその「論説文」の大意(要点)をつかみ、筆者が何を主張したかったのかをとらえるようにします。
つまり、そこにどんな事実が書かれており、それに対して筆者はどんな考えを持っているのかをつかむのです。大意(要点)をきちんと捉えられているかどうかを親御さまとお子さまとで口頭で確認するのも一つの有効な方法です。
そのことを繰り返し行うことで、「論説文」の文章構成に次第に慣れていきます。
また、自然に読むスピードも速くなり語彙力もついてきます。
「説明文」「物語文」「随筆文」も同様です。
もし、それらの文章で問題の正解が得られていないようでしたら、なるべくそのジャンルの文章を読むようにします。
読みながら文章の大意(要点)をとらえる、筆者がどんなことを考え、述べたかったのかをつかみ取ることも必ず行って下さい。
次に、読解問題の場合、落としている設問形式をチェックします。
中学受験の設問形式は、3つあるということは、『中学入試 国語の読解は答え探しの技で勝つ!』の著書の中でも述べておりますが、どの形式で正解が得られていないのかを必ず分析して下さい。
そして、その3つのパターンである、「選択式」「抜き出し式」「記述式」の弱い部分を補習する必要がありますので、著書の中に掲載しております「設問の解き方テクニック」の部分を参照しながら形式別に学習して下さい。
ここで一番肝心なことは、設問の答えの根拠をきちんと問題文の中に求めているかどうかです。
必ず、そこをチェックして下さい。もし、それができていなかった場合は、そのテストの復習をする際には、「答えや答えの手がかり」が問題文のどこに書かれてあったのかをお子さまと確認するようにして下さい。
そして、次にどのように間違えてしまったのかをチェックします。
↓
間違え方には大まかに分類すると次のようなものがあります。
設問を読み間違えてしまった場合
設問を読み間違えたことをただ単に「オッチョコチョイ」で片づけてはいけません。設問の読み間違えというのは、「何を聞かれて何をどのように答えなければならないのか」ということを頭の中で理解できていないことが多いのです。
そのままにしていては、設問の読み間違えをずっと繰り返してしまいますので、すぐに読み間違えをしないように訓練する必要があります。
この「設問を読み間違える」ということは訓練次第で克服することができます。
是非、『中学入試 国語の読解は答え探しの技で勝つ!』に掲載している「設問文の読み方テクニック」の内容を繰り返し実行して下さい。
設問を正確に読み解答するためには、とにかく読解問題に取り組む際には「設問文の読み方テクニック」を必ず毎回実効することです。
「前回勉強した時には実行したのに今回は実行しない」というように、「やったりやらなかったり」というのでは、なかなか軌道修正ができません。
ここで申し上げておきたいのは、
「設問文の読み間違い」というのを完全になくすためには、個人差はあるもののかなりの時間がかかります。
例えば、「先週はきちんとできて正解が得られたのに、今日はできなかった」ということの繰り返しです。どのお子さまも「いっぺんで完璧に読み間違えなくなる」ということはありません。
ですから、読解問題を解く際には根気良く毎回実行することが必要です。-
解答する際に問題文の中からその根拠を求めずに、
自分の考えだけで答えてしまっている場合
このようなケースは、すぐに「国語の基本的な解法」を学習しなければなりません。お子さまが問題文の中に答えの根拠を求めることなく独自の考えをもとに解答してしまう習慣がついてしまうと「問題文が自分の感性にピッタリとはまった場合は面白いほどに正解が得られる」という反面、「問題文が自分の感性と合わない場合は、ほとんど正解が得られなくなる」という可能性があります。
よく、「国語が得意科目なのか不得意科目なのかわからない」というほどテストを行うとその都度、「毎回のテストの点数に大きな開きが出てしまう」というお子さまがいらっしゃいます。
その原因は、つきつめていくと、設問の答えを問題文に書かれている内容から根拠を探し、そこを踏まえて答えられていないだけなのです。
ですから、もし、その基本的な解法ができていない場合は、テストの復習をする際に、「その設問の答えや答えの手がかりが問題文のどこに書かれているのか」ということを必ず確認して、できれば、その文章に印をつけて線を引いて下さい。
そして、改めてもう一度答えの根拠を問題文中に確認しながら問題文と設問を読んで下さい。
「答えの手がかり」を再度確認して文章を読むことにより、その問題文の内容がより一層理解できるはずです。
是非実行してみて下さい。