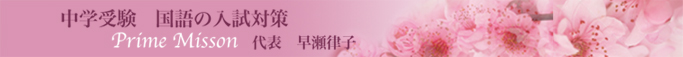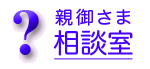<暗記科目を制覇するコツ>
「暗記をする」ために時間をかけて学習したつもりでも、断面的なものを単発で記憶させるという方法では、なかなか覚えられません。
例えば、社会は暗記科目とよくいわれていますが、ただ事実を頭の中に叩き込むだけでは、記憶として残りにくいし、それになによりも入試問題を解く際に対応しきれません。
入試問題においては、一つの事実について様々な角度から質問の矢が飛んできます。したがって、それに対応できる応用力が必要になります。
しかし、それは事実の断片を一つずつ覚えているという状態では対応しきれるものではないのです。
今回は親御さまからのご要望が多かったので社会を例に挙げます。
例えば、歴史の学習方法についてですが、年号や事件を時代ごとに暗記することはもちろん大切なことです。
しかし、これを一つの事実だけ断片的に切り取って覚えていても記憶にそれをとどめておくのは難しいし、ちょっとひねった問題が出てしまうと解答しきれないということになります。
では、どのように覚えていけばいいのでしょうか?
例えば、歴史というのは常に動いて流れていくものです。
その流れをしっかりとすべてを総合的にとらえて覚えていくことです。
人は、類人猿から狩猟や採集の生活を経て農耕生活を始め、その中で共同生活を行うようになりました。
集団ができると強い人と弱い人、また食料の蓄えの多い者と蓄えの少ない者、あるいはまったく蓄えのない者、といったように身分の差が必然的にでてきます。
身分の差がでてくるとその集団のリーダーが決まります。
さらに生活を続けていくうちに人間同士は当然いろいろな利権を争うようになり、その争いの結果、勝ったものがまた新しいリーダーとして出現します。
リーダーが物理的に歳をとり高齢になればその力は失われます。そしてまた新しいリーダーが登場します。
集団で生活すれば、いろいろな決まりごとをつくらなければ秩序が保てず生活に混乱をきたします。そこで今でいう法律のような「きまり」ができます。
法律ができれば、自ずと制度ができます。
このように人間が生活をしていく上で自然に歴史は流れていくものです。
ですから歴史を学習する時には、この流れを総括的につかんでいくと一つ一つの出来事も記憶として定着し易いのです。
先ほど述べましたことを簡単に図式化してみます。
ある時代の社会生活(既成のリーダーが司る政治、経済、制度、文化)
↓
問題発生(主に利権をめぐる問題)
↓
争いが起きる(戦争)
↓
戦争の結果で新しいリーダーが出現する
↓
リーダーが変われば政治が変わる
↓
政治が変われば制度が変わる
↓
政治と制度が変われば経済が変わる
↓
政治と制度と経済が変われば文化が変わる
このように一つの事実はさまざまな背景と結びついています。
歴史の一つの事実を断片的にそれだけで覚えていても記憶にそれを残していくのは難しいのですが、上記したような流れが総括的に頭に入っていれば逆に忘れなくなります。物事には理由があります。その理由をきちんと把握した上で一つ一つの事実をその時代背景とリンクさせて結びつけていきながら丁寧に年号や事件を記憶させていくのです。
これを現在の私たちの社会生活に置き換えても同じことがいえます。
小泉内閣、阿部内閣、福田内閣の流れの中では、やはり政治、制度、経済が微妙に変化しています。そして、その流れに即した形で文化が生まれていきます。その一連の流れを把握しながら丁寧に一つ一つの事実を記憶させていくことが大切です。
地理も同様です。その地方の気候や土地の条件などにより、収穫できる農産物や発達する産業は異なります。
ただ断片的に「・・・の生産地は・・・」という覚え方ではなかなか頭にスッと入っていかないし、それを記憶として定着させるのは難しいのです。
地理の苦手なお子さまの多くは、そもそもその地方の地形そのもののイメージが頭の中に浮かんでこないことがネックになっています。
例えば、みかんの生産地を覚える時には、まずその土地の地形、気候をイメージして「なぜ、その土地ではみかんがたくさん実るのか」ということを最初に理解することが大切です。
また、食卓でみかんを食べる時に、お母さまが、「このみかんは、愛媛産か、和歌山産か、静岡産か当ててみて?」などと、会話に組み込むのも効果的です。
するとお子さまは「みかんが愛媛県、和歌山県、静岡県でたくさん実る」ということを忘れません。お子さまご自身がみかんの皮を手でむき、香りをかいで、食べることによりその美味しさを味わい、人間の五感すべてを使いながら楽しい会話をお母さまと交わしたのですから忘れるわけがありません。
食卓を囲む時に、家族で「これは・・・産の・・・だよ」などと、食べながら野菜の産地の話をすると楽しいので是非やってみて下さい。あくまで、「勉強をする」という意識ではなく、親子の日常会話として楽しむことがコツです。
公民も同様です。特に政治や経済のニュースはビデオに録画しておいてお子さまが勉強に疲れて休憩する時に見るようにするといいです。
お子さまの気分転換にもなりますし、テキストの中で学習した内容が具体的な映像と音声とで頭の中で結びつく形でインプットされていきますのでお勧めです。
そして、その内容について会話を弾ませていくと楽しいです。
「小泉さんの頭はライオンみたいね」「福田さんは、中国では、ドラエモンに出てくるのび太君に似ているっていわれているんですって」など気楽な会話でいいのです。
親子で楽しく話した内容は無理なく頭の中に記憶として残ります。
話が楽しければ、お子さまはもっとそのことについて知りたいという欲求が自然に湧いてきますので意欲的になります。
また、テキストや新聞を読んだり、参考書や資料を活用してさらに調べたいという気持ちも湧いてきます。
社会という科目は、親子で会話が楽しめるネタが盛りだくさんです。
中学受験は非常にいいチャンスですので、これをきっかけとして「社会ネタ」を盛り込んで会話をしながら親子で遊んでみて下さい。